Category:お役立ち情報

自分らしい働き方や診療スタイルを実現するため、勤務医から開業医へ転身しようと考えている方も多いでしょう。
しかし、クリニックの倒産件数や人手不足などによる休廃業・解散件数は増加傾向にあります。東京商工リサーチの調べによると、2024年の病院やクリニック(診療所)、歯科医院の倒産件数は64件となり、過去20年で最多件数を更新しました(※)。
クリニックの開業を成功させるためには、しっかりと診療圏調査を行い、計画的に開業準備を進めていくことが大切です。この記事では、クリニックの開業に必要な手順や、開業費用の目安、内装工事や集患・増患のポイントをわかりやすく解説します。
※株式会社東京商工リサーチ「2024年の医療機関の倒産が過去20年で最多 クリニック、歯科医院が押し上げ、病院も3.5倍増」
≪クリニックの開業は医師のキャリアにおいて重要な選択肢≫
クリニックの開業とは、医療施設で働く勤務医の方が開業医として病院や診療所の経営を始めることを指します。開業する方法には、自分で物件を探し一から医院づくりを進めていく「新規開業」と、既存のクリニックの経営を引き継ぐ「承継開業」の2種類があります。
厚生労働省の「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医療施設の開設者・勤務者の数は以下の表の通りです(※1)。
| 病院 | 開設者または法人の代表者 | 5,251人 | |
| 勤務者 | 医育機関附属の病院以外 | 15万5,175人 | |
| 医育機関附属の病院 | 5万9,670人 | ||
| 従事者全体 | 22万96人 | ||
| 診療所 | 開設者または法人の代表者 | 7万360人 | |
| 勤務者 | 3万6,988人 | ||
| 従事者全体 | 10万7,348人 | ||
病院・診療所を合わせた開業医の数は7万5,611人と、医療施設の従事者全体の約23%を占めています。特に1名以上の医師数で開業できる診療所(※2)では、医師の約65.5%が開業医であり、自分のクリニックを開き新たなキャリアの一歩を踏み出す方が増えています。
※1 厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」p1
※2 文部科学省「大学等と病院・診療所」p1
≪クリニックを開業する4つのメリット≫
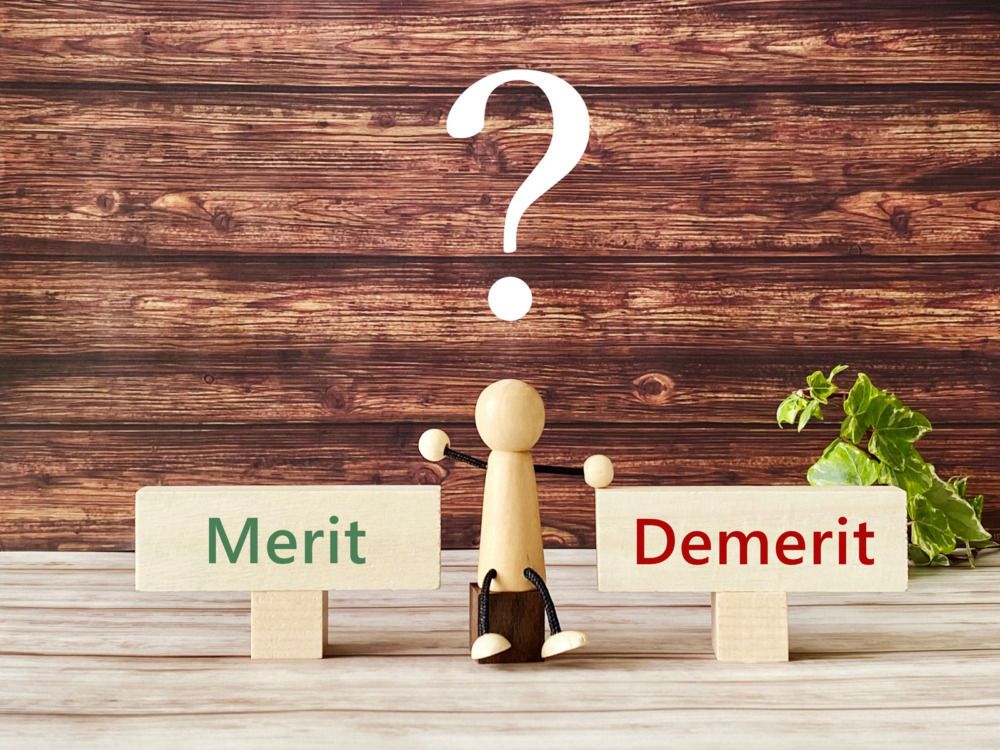
クリニックを開業するメリットは4つあります。
- ●勤務医よりも収入が多い傾向にある
- ●自分の裁量で働き方や診療スタイルを決められる
- ●人間関係によるストレスを減らせる
- ●医療を通じて生まれ育った地域に貢献できる
クリニックを開業すれば、勤務医時代よりも収入が大きく増える可能性があります。厚生労働省の「第24回医療経済実態調査(令和5年実施)」によると、病院に所属する医師の平均年収が1,461万739円であるのに対し、一般診療所の開設者(院長)の平均年収は2,631万3,306円です(※)。勤務医の平均年収と比べ、約1.8倍も上回っています。
クリニック開業のメリットは、経済的な面だけではありません。自分のクリニックを持てば、働き方や診療スタイルを独自の裁量で決められます。医局内の派閥争いなどもないため、人間関係によるストレスも軽減できるでしょう。
また医療を通じて、自分が生まれ育った地域に貢献できるのもメリットです。自分のクリニックなら、クリニックの外観や内装、導入する医療機器なども自由に決められるため、勤務医時代には叶えられなかった夢を実現できるでしょう。
※厚生労働省「第24回医療経済実態調査(令和5年実施)」p302、560
≪クリニックを開業する3つのデメリット≫
クリニックの開業は、メリットばかりではありません。クリニックを開業するデメリットは3つあります。
- ●勤務医と比べ、収入面の安定性に欠ける
- ●経営者として資金繰りを自ら行う必要がある
- ●集患やスタッフの労務管理などの業務負担が発生する
開業医は、勤務医と違って固定給をもらえるわけではないため、収入が不安定になりがちです。クリニックの経営状況が安定せず、患者の数が減ってしまった場合、収入がほとんど得られなくなる可能性もあります。
また勤務医と比べ、開業医はやらなければならない仕事も増えます。クリニックの経営者として、資金繰りにしっかりと取り組み、支払いが滞ることがないように収入や支出を管理しなければなりません。クリニックに患者を呼び込むための集患・増患対策や、従業員の労務管理なども必要です。万が一、医療をめぐる訴訟やトラブルが起きた場合、院長として矢面に立つ場面も出てきます。
クリニックを開業すると、勤務医にはない自由を手にできる一方で、経営者としての責任や負担が増えるという側面もあることを知っておきましょう。
≪クリニック開業の基本的な流れ≫
ここでは、クリニック開業の基本的な流れを11のステップに分けて解説します。
- 1.開業したいエリアの診療圏調査を行う
- 2.クリニックの事業計画書を作成する
- 3.開業する場所や物件を選ぶ
- 4.地域の保健所や医師会と事前相談を行う
- 5.金融機関などから開業資金を調達する
- 6.内装・デザイン会社を選ぶ
- 7.導入する医療機器を選ぶ
- 8.開業に必要な行政手続きを行う
- 9.税理士や公認会計士と契約する
- 10.スタッフの求人・採用を行う
- 11.集患・増患のためのPR活動に取り組む
1. 開業したいエリアの診療圏調査を行う
クリニックの開業に先立って、開業したいエリアの診療圏調査を行いましょう。診療圏調査とは、その地域の人口や年齢層、男女比率、競合するクリニックなどを調べ、開業後にどの程度の患者数が見込めるかを予測する調査です。
- ●診療圏内の人口や年齢層を調べる
- ●競合となるクリニックの数や評判を調べる
- ●立地条件や交通アクセスを調べる
【診療圏内の人口や年齢層を調べる】
まずは開業予定地から500メートル~1キロメートル以内のエリアを診療圏に設定し、その地域の人口や年齢層を調べましょう。診療圏の人口構成によって、ターゲットとすべき患者層が異なります。
- ●子どもが多いか
- ●生産年齢人口(15~64歳)が多いか
- ●高齢者・シニア世代が多いか
- ●ファミリー層が多いか
- ●単身者が多いか
例えば、子どもの数が多く、生産年齢人口の割合が高いエリアであれば、小児科やファミリー向けのクリニックの開業に適しています。診療圏調査に基づいて、開業したいクリニックのコンセプトに合ったエリアを探しましょう。
【競合となるクリニックの数や評判を調べる】
診療圏調査では、その地域の競合クリニックの数や評判を調べることも大切です。一般的に、競合クリニックの数が多い地域ほど、患者数の確保が難しくなります。集患で困らないためには、同じ診療科目のクリニックが少ないエリアを選ぶとよいでしょう。
ただし、競合クリニックによって集患状況はさまざまです。競合クリニックの数が多いエリアでも、「設備や医療機器が古い」「待ち時間が長い」など、既存のクリニックの評判があまり良くない場合、開業後に一定の患者数を見込める可能性があります。
クリニックの集患状況は、直接足を運ばないとわからないことも多いため、実際に見に行ってみることをおすすめします。
【立地条件や交通アクセスを調べる】
診療圏の立地条件や交通アクセスも調べましょう。集患する上で、駅やバスターミナルの近くなど、公共交通機関のアクセスが良好なエリアで開業した方が有利です。また通院しやすい場所にクリニックがあると、スタッフも募集しやすくなります。
ただし、精神科や心療内科など、人通りが少ない地域で開業した方が集患しやすい診療科目もあります。また立地条件が良い物件は、家賃などの費用負担も重い傾向にあるため、採算が合うかどうかをしっかりと検討しましょう。
2.クリニックの事業計画書を作成する

クリニックの開業で失敗しないためには、頭の中で思い描く構想を事業計画として整理し、目標や事業内容を明確化しておくことが大切です。
また事業計画を記載した事業計画書は、金融機関から融資を受けたり、補助金や助成金を申請したりする際に提出する必要があります。自分だけでなく、他人が読んでも理解できるように事業計画書を作成しましょう。
- ●クリニックのコンセプトや方針を決める
- ●必要な資金と調達方法を考える
- ●開業までのスケジュールを立てる
【クリニックのコンセプトや方針を決める】
まずはクリニックのコンセプトや方針を決めましょう。あらかじめコンセプトをはっきりさせていないと、開業後に軌道修正が必要となり、無駄なコストが発生してしまいます。以下のような観点から、「どのような医院づくりをしたいか」を明確化しましょう。
- ●どのような診療がしたいのか
- ●医師としての強みや得意分野は何か
- ●どのような患者層をターゲットとするか
- ●地域の人々にどのように思われたいか
事前に診療圏調査を行っていると、その地域で求められる医療やクリニック像をイメージしやすくなります。
【必要な資金と調達方法を考える】
次に開業に必要な資金と、その調達方法をそれぞれ考えましょう。事業計画書では、資金計画と呼ばれる項目です。以下のように「必要な資金」と「調達方法」の項目に分け、具体的な金額を記載しましょう。
| 必要な資金 | 設備資金(内装工事費用や医療機器の購入費用など) |
| 運転資金(人件費や家賃など) | |
| 調達方法 | 自己資金 |
| 親族などからの借り入れ | |
| 金融機関からの借り入れ |
金融機関から融資を受けたい場合は、資金計画だけでなく、損益計画も作成しておくことをおすすめします。損益計画とは、開業後の収入や支出の見通しに基づき、将来どの程度の利益が見込めるかをまとめた表です。損益計画に沿って事業を営むことで、クリニックの経営を健全化できます。
【開業までのスケジュールを立てる】
最後にクリニックを開業するまでのスケジュールを決めましょう。以下の表のように開業予定日から逆算して考えると、スケジュールを立てやすくなります。
| 開業までの期間 | 実施項目の例 |
| 7~9カ月前 | ●診療圏調査 ●開業物件選び ●保健所・医師会への事前相談 ●融資担当者との面談 ●医療機器の選定など |
| 4~6カ月前 | ●開業物件の契約 ●融資の申し込み ●医療機器の購入・リース契約 ●内装工事業者の選定 ●ホームページ業者の選定 ●税理士・公認会計士の選定など |
| 1~3カ月前 | ●内装工事完了・引き渡し ●従業員の求人募集・面接 ●ホームページの制作 ●チラシ・印刷物の制作 ●税理士・公認会計士との顧問契約 ●備品・什器の購入 ●保健所・医師会の手続き ●開設届などの行政手続き ●従業員の研修など |
事業計画書では、1月~3月、4月~6月、7月~9月など、3カ月ごとに実施項目を記載することが一般的です。
3. 開業する場所や物件を選ぶ
クリニックの開業で失敗しないためには、開業する場所や物件選びが重要です。ターゲットとなる患者層と合わない場所で開業すれば、集患に大きく苦労することになります。
開業物件には、戸建てやビルテナント、医療モール(クリニックモール)のテナントなど、さまざまな種類があります。診療圏調査の結果も参考にしながら、クリニックのコンセプトに合った物件を選びましょう。
- ●クリニックのコンセプトに合った場所を選ぶ
- ●開業する物件の種類を選ぶ
- ●公共交通機関などのアクセスの良さも確認する
【クリニックのコンセプトに合った場所を選ぶ】
せっかくクリニックを開業しても、立地条件が悪く、集患がうまくいかなければ収益を上げられません。開業する場所を選ぶときは、クリニックのコンセプトに合う立地かどうかを慎重に検討する必要があります。診療圏調査に基づいて、ターゲットとなる患者層が多いエリアを選びましょう。
ただし、診療圏調査の数字だけでは、本当に開業に適した場所かどうかはわかりません。データ上は競合クリニックが少なく、好立地に見える場所でも、実際に足を運んでみると、地域の住民にとって通いにくい立地であるケースもあります。
クリニックのコンセプトに合った場所かどうか、自分の目で確認してみることも大切です。
【開業する物件の種類を選ぶ】
クリニックの開業場所は、戸建て、ビルテナント、医療モール(クリニックモール)の3種類に分けられます。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
| 戸建て | ●外観や内装の自由度が高く、予算の範囲内で理想の医院づくりができる ●駐車場を設ければ、より広い診療圏の患者にアピールできる |
●一から新築する必要があるため、開業までの日数やコストがかかる ●近くに調剤薬局がない場合、院内処方を行う必要がある |
| ビルテナント | ●駅の周辺や繁華街など、好立地の物件が多い ●初期費用が少なく、金融機関からの融資が受けやすい ●前にクリニックがあった居抜き物件なら、さらにコストを抑えられる |
●戸建てと比べ、外観や内装の自由度が低い ●ビルの管理者によって、看板などの設置に制限がある |
| 医療モール(クリニックモール) | ●医療施設が一箇所に集まっているため、集患・増患が期待できる ●電気設備や給排水設備などのインフラが、医療機関向けであることが多い ●看板を設置するスペースや、外来患者用の駐車場が用意されていることが多い |
●モール内に競合のクリニックがある場合、患者の奪い合いになる ●同じ診療科目のクリニックが出店している場合、事前に協議が必要になる ●内装工事業者などが、モールの管理会社から指定されている場合が多い |
【公共交通機関などのアクセスの良さも確認する】
電車やバスなど、公共交通機関へのアクセスの良さも確認しましょう。特に専門性の高い医療を提供するクリニックの場合、広い範囲から患者を集める必要があります。ターミナル駅の近くなど、交通アクセスの良い物件を選ぶことが大切です。
一般的に以下のような立地であれば、患者数を確保しやすいと言われています。
- ●駅から近く、通勤・通学の経路上にある
- ●線道路沿いにあり、大型の商業施設が近くにある
- ●スーパーやコンビニが近くにあり、住民の生活動線上にある
診療圏調査の結果や、近隣のクリニックの評判なども考慮しながら、集患が見込めそうな場所を探しましょう。
4. 地域の保健所や医師会と事前相談を行う
クリニックを開業するには、「診療所開設届」を提出する必要があります。開業直前になって不備が出ないように、保健所から事前相談を求められることが一般的です。
事前相談の場では、クリニックの名称や診療科目のほか、地域医療への協力の意思などを確認される場合があります。クリニックの図面(平面図)なども、内装工事業者から受け取り次第、保健所に提出しておくとよいでしょう。
また医師会に加入する場合も、管轄の医師会事務所と事前相談を行う必要があります。クリニックの開業に関してアドバイスを受けられる場合もあるため、加入の意思にかかわらず、一度訪問しておくとよいでしょう。
5. 金融機関などから開業資金を調達する
クリニックの開業には、内装工事の費用や医療機器の購入費用など、多額の資金が必要です。自己資金のみで開業資金を捻出できない場合は、金融機関などからの借り入れを検討しましょう。
また開業する地域によっては、補助金や助成金の交付を受けられるケースがあります。返済が不要な制度もあるため、クリニックの開業に活用できるものがないか確認しておくとよいでしょう。
- ●融資を受ける金融機関を選ぶ
- ●補助金・助成金を活用する
【融資を受ける金融機関を選ぶ】
クリニックを開業する方の多くが、金融機関からの借り入れを行っています。一般的に、自己資金が多い方ほど有利な条件で融資を受けられますが、自己資金がほとんどない方向けのローンもあります。ただし、開業後は人件費や家賃とともにローンの返済を行っていく必要があるため、無理のない範囲で借り入れを行いましょう。
融資を受けられる金融機関には、以下のような種類があります。
| 金融機関の種類 | 特徴 |
| 都市銀行(メガバンク) | ●金利が低く、大規模な融資を受けられる ●少額の融資には対応していないケースが多い ●審査が厳しく、事業経験がない方は融資を受けられない可能性が高い |
| 地方銀行 | ●その地域で開業するクリニックのみ融資を受けられる ●都市銀行と比べ、融資条件がゆるやかな銀行が多い |
| 信用金庫・信用組合 | ●地方銀行と比べ、小規模の事業者が対象 ●医師会に加入したクリニック限定のローンもある |
| 政府系金融機関(日本政策金融公庫) | ●中小規模の事業者を対象とした融資制度が充実している ●金利が低く、無担保・無保証人で融資を受けられる制度もある ●返済期間が長く設定されており、月々の返済負担が小さい |
【補助金・助成金を活用する】
補助金・助成金とは、国や自治体が事業者の取り組みを支援するため、資金の一部を交付する制度です。補助金・助成金を活用するには、募集要項に則った審査を受ける必要があります。また資金の給付は原則として後払いのため、補助金・助成金のみに頼って開業することはできません。
クリニックを開業する地域によっては、自治体が運営する助成金や補助金の交付を受けられます。例えば、京都府での開業なら「起業支援事業費補助金」、大阪府での開業なら「開業・スタートアップ応援資金」の申し込みが可能です。
助成金や補助金によって、申し込みの時期や融資条件が異なるため、自治体のホームページなどを確認してください。
6. 内装・デザイン会社を選ぶ

開業する物件が決まった段階で、内装・デザイン会社を探しましょう。内装工事が完了するまでは時間がかかります。テナントを借りる場合は開業の6カ月前、一から新築する場合は開業の1年前を目安として、スケジュールに余裕を持って内装工事を発注しましょう。
また内装・デザイン会社によって、得意とする分野が異なります。医療施設の設計・内装では、遵守しなければならない法令も多いため、クリニックの施工実績が豊富な事業者を選ぶことが大切です。
7. 導入する医療機器を選ぶ
内装・デザイン会社選びと並行して、導入する医療機器の選定も行いましょう。
近年は医療サービスの効率化の観点から、診療科目ごとに必要な医療機器に加えて、電子カルテを導入するクリニックが増えています。電子カルテの導入には、中小企業庁が募集する「IT導入補助金」などの補助金の活用も可能です。
なお、診療用のエックス線装置(レントゲン)を導入する場合は、クリニック所在地の自治体に対し、設置後10日以内(※)に届出を行う必要があります。
※京都市「病院・診療所の診療用エックス線装置等に係る届出について」
8. 開業に必要な行政手続きを行う
クリニックの開業には、さまざまな行政手続きが必要です。医療施設の開設に関する提出書類として、以下のようなものが挙げられます(※)。
| 提出書類 | 提出先 | 期限 |
| 診療所解説届 | 保健所 | 開設後10日以内 |
| 診療用エックス線装置備付届 | 備付後10日以内 | |
| 診療所使用許可申請書(有床診療所の場合) | 開設前 | |
| 保険医登録申請書 | 社会保険事務所 | 開設前 |
| 保険医療機関指定申請書 | 開設前 |
その他、税務署に提出する書類(個人事業主の開業届や、青色申告承認申請書など)や、社会保険に関する手続き(健康保険・厚生年金保険の新規適用届など)も忘れずに行いましょう。
※京都府「医療機関等の手続き」
※京都市「病院・診療所の診療用エックス線装置等に係る届出について」
9. 税理士や公認会計士と契約する
クリニックの会計・税務に関して、専門家に相談したい方は、税理士や公認会計士との顧問契約を締結しましょう。税理士や公認会計士には独占業務があり、それぞれできることが異なります。
税理士と顧問契約を結ぶと、手間のかかる税務申告を代わりに行ってもらえるほか、税金に関するさまざまなアドバイス(税務相談)を受けられます。
資金計画の作成や資金繰りなど、会計に関する相談をしたい場合は、公認会計士との契約を検討するとよいでしょう。
10. スタッフの求人・採用を行う
クリニックには、看護師や受付の事務員などのスタッフも欠かせません。診療科によっては、理学療法士や作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師などの医療従事者の採用も必要です。
近年、医療従事者は慢性的な人手不足の状態にあると言われています。特に経験豊富なスタッフの採用には時間がかかるため、遅くとも開業の3カ月前を目安として求人募集を行いましょう。
11. 集患・増患のためのPR活動に取り組む
開業後に患者数を確保するには、PR活動も重要です。印刷物(チラシ)の配布やホームページの作成、SNSの運用、広告看板の設置など、さまざまな手法を駆使して、集患・増患対策に取り組みましょう。
≪クリニック開業に必要な資金の目安≫

ここでは、クリニックの開業資金の目安や内訳、診療科別の違いを紹介します。
クリニックの開業資金の目安は5,000万~8,000万円
クリニックを新規開業する場合、必要な資金の目安は5,000万~8,000万円程度です。開業資金の大部分は内装工事費や医療機器の購入費用が占めています。
それ以外にも、テナントの前家賃や什器・備品の購入費用、広告宣伝費用、開業後の運転資金などが必要です。
【テナントの前家賃・保証金】
テナントの前家賃とは、賃貸契約を締結するにあたって、前もって家賃を納めることを指します。事業用の物件の場合、3カ月分の前家賃の支払いを求められることが一般的です。
その他、テナントによっては敷金や保証金、礼金などの支払いが必要です。不動産会社から物件の仲介を受けた場合は、仲介手数料も発生します。
【内装工事費用】
内装工事費用とは、クリニックの壁や床、天井の仕上げ工事や、照明の設置工事、電気・水道・ガスなどの設備工事にかかる費用を指します。
内装工事費用は、建物の床面積1坪(約3.3㎡)あたりの「坪単価」で表すことが一般的です。診療科にもよりますが、クリニックの場合は坪単価60万~70万円程度が目安となります。
【医療機器の購入費用】
内装工事費用とともに開業資金の大部分を占めるのが、医療機器の購入費用です。体温計やメスなどの小型機器から、X線CTやMRIなどの大型機器まで、さまざまな種類があります。
大型の医療機器は納入まで時間がかかるため、必要な医療機器のリストを作成し、早めに購入手続きを進めましょう。
【什器・備品の購入費用】
医療機器だけでなく、日々の診療に使用する什器・備品の購入も必要です。玄関や受付、待合室、診察室、トイレなど、院内の施設によって必要な什器・備品が異なります。
以下の表は、クリニックの開業に必要な什器・備品の一例です。
| 玄関 | 玄関マット、下駄箱、スリッパ、傘立てなど |
| 受付 | 診察券入れ、筆記用具、時計、カレンダー、パソコン、プリンター、コピー用紙など |
| 待合室 | ソファ、時計、テレビ、雑誌、マガジンラック、ゴミ箱、空気清浄機、ウォーターサーバーなど |
| 診察室 | 診察ベッド、診察机、椅子、聴診器、消毒器具、衛生材料など |
【広告宣伝費用】
クリニックのPR活動のため、印刷物(チラシ)を作成したり、ホームページを制作したりする場合、広告宣伝費用もかかります。診療科にもよりますが、広告宣伝費用の目安は300万円程度です。
無料でアカウントを開設できるSNSの運用や、Googleマップなどを用いたMEO対策など、比較的コストがかからない宣伝方法もあります。
【開業後の運転資金】
クリニックの開業後、集患に苦戦する可能性もあります。経営が軌道に乗らない場合を想定して、開業後の運転資金(家賃や人件費など)を半年から1年分、用意しておくとよいでしょう。
診療科別の内装工事費用の目安
クリニックの内装工事に必要な費用は、診療科目によって異なります。以下の表は、診療科別の内装工事費用の目安です。
| 診療科目 | 内装工事の目安 |
| 脳外科 | 約6,500万円 |
| 整形外科 | 約4,000万円 |
| 内科 | 約3,000万円 |
| 小児科 | 約2,500万円 |
| 眼科 | 約2,500万円 |
| 耳鼻科 | 約2,500万円 |
| 皮膚科 | 約2,000万円 |
実際の内装工事費用は、クリニックの広さ(敷地面積)や、物件状況などによって異なるため、施工会社にお問い合わせください。
初期費用と運転資金の違い
クリニックの開業にあたって知っておく必要があるのが、初期費用と運転資金の違いです。
初期費用とは、イニシャルコストとも呼ばれ、内装工事費用や医療機器の購入費用、テナントの入居費用など、開業までに発生する費用を指します。
一方、運転資金は、開業後にクリニックを経営する上で必要となるランニングコストです。例えば、テナントの家賃や水道光熱費、医療機器のリース料金、従業員の人件費など、月々に発生する支払いが該当します。
初期費用と運転資金の両面から、クリニックの事業計画を策定し、資金繰りを行いましょう。
≪クリニックの内装で注意すべきポイント≫

ここでは、クリニックの内装を決めるときに注意したいポイントを4つ紹介します。
- ●患者やスタッフの動線を意識した設計にする
- ●明るく清潔感のあるデザインにする
- ●消毒・メンテナンスがしやすい素材を使用する
- ●クリニックの施工実績が豊富な業者に依頼する
患者やスタッフの動線を意識した設計にする
クリニックの内装工事では、患者やスタッフの移動の流れに合わせてレイアウトを設計する「動線計画」が重要です。動線には、患者動線・スタッフ動線・裏動線の3種類があります。
【患者動線】
患者動線とは、患者が来院してから会計を終えて退院するまでの移動の流れのことです。患者動線を考慮してレイアウトを設計することで、患者様がストレスを感じることなく、スムーズに診療を受けられます。
【スタッフ動線】
スタッフ動線とは、診察の際に医師や看護師が院内を移動する流れのことです。クリニックのレイアウトを設計する際は、スタッフが無駄なく移動できるように工夫するとともに、患者動線とスタッフ動線が交わる場所を最小限に抑える必要があります。
【裏動線】
患者動線とスタッフ動線を分ける上で大切なのが、裏動線の存在です。裏動線とは、スタッフのみが利用する場所や通路のことを指します。スタッフが作業するバックヤードや、休憩中に利用するスタッフルームなど、患者様に見せたくない場所にも裏動線を配置します。
明るく清潔感のあるデザインにする
クリニックは、さまざまな悩みや不安を抱えた方が、治療を受けるために訪れる場所です。明るく清潔感のある空間づくりを意識して、クリニックの内装デザインを考えましょう。
清潔感や開放感をイメージさせる白を基調としつつ、落ち着いた色のアクセントカラーを加えることで、居心地の良い医院づくりにつながります。
消毒・メンテナンスがしやすい素材を使用する
壁材や床材など、クリニックの内装に使用する仕上げ材には、耐久性が高く、消毒やメンテナンスがしやすいものを選びましょう。
医療機関では、院内の清潔さを維持するため、繰り返し消毒や清掃を行います。消毒用のエタノールや次亜塩素酸ナトリウムに弱い仕上げ材を使用すると、すぐに経年劣化が起きてしまう可能性があります。
クリニックの内装の実績がある業者に依頼する
クリニックの内装工事会社を選ぶポイントは3つあります。
- ●実際の施工事例を確認できるか
- ●工事にかかる費用や期間が明確か
- ●アフターフォローがしっかりしているか
【実際の施工事例を確認できるか】
内装工事を依頼するときは、クリニックの施工実績が豊富な業者を選びましょう。施工実績は、内装工事会社のホームページやSNSなどに掲載されていることが一般的です。内装デザインの仕上がりイメージを確認するため、写真付きの施工事例をチェックするとよいでしょう。
【工事にかかる費用や期間が明確か】
ホームページなどに、工事費用や工事期間の目安が記載されているかも確認しましょう。工事にかかる費用の見積もりや、開業までのスケジュールが立てやすくなります。
工事費用が記載されていない場合は、掲載されている施工実績を確認し、イメージに近い事例から費用を概算するとよいでしょう。
【アフターフォローがしっかりしているか】
クリニックの内装は、工事が完了したら終わりではありません。定期的に修繕やメンテナンスを実施し、経年劣化を防ぐ必要があります。
内装工事が完了した後も、定期点検などの保証やアフターフォローを受けられる業者を選びましょう。アフターフォローが充実した内装工事会社なら、万が一、引き渡し後に施工不良が見つかっても迅速に対応してくれます。
≪クリニックの集患・増患につながる施策≫

ここでは、クリニックの集患・増患につながる施策を4つ紹介します。
- ●クリニックのホームページを制作する
- ●印刷物(チラシ)のポスティングをする
- ●目立つ場所に広告看板を設置する
- ●SEO対策やMEO対策を実施する
クリニックのホームページを制作する
クリニックのホームページは、患者様が医療機関を選ぶ上で重要な情報源となります。クリニックの公式ホームページを制作し、医療サービスに関する情報を発信していくことで、集患・増患につながるでしょう。
またスマートフォンが普及した今、インターネットで検索し、通院先を探す方が増えています。多くの患者様にクリニックの存在を知ってもらう上でも、ホームページの制作は必要不可欠です。
印刷物(チラシ)のポスティングをする
ホームページでの集客と合わせて、印刷物(チラシ)のポスティングも行うとよいでしょう。
ポスティングには、エリアやターゲットを絞って宣伝できるという強みがあります。クリニック周辺の診療圏でポスティングを実施することで、効率的に集患できます。
目立つ場所に広告看板を設置する
駅看板や野立て看板などの看板を設置すると、クリニックの存在を認知してもらいやすくなります。通行人の記憶に残りやすいように、目立つ場所に看板を設置しましょう。
ただし、ビルテナントで開業する場合は、管理会社の意向により、看板を設置できない可能性があります。また自治体によっては、看板設置に関するルールや条例が定められている場合があるため、事前に確認しましょう。
SEO対策やMEO対策を実施する
インターネットを通じて集患する場合は、SEO対策やMEO対策が重要です。
| SEO対策 | Googleなどの検索エンジンにおいて、ホームページの検索順位を上げるための施策 |
| MEO対策 | Googleマップなどの地図情報サービスにおいて、自身の店舗が上位に表示されるようにする施策 |
近年では、Googleマップなどの地図情報サービスを利用して、近くの医療機関を探す方も増えています。SEO対策に加えてMEO対策を実施することで、集患・増患につながるでしょう。
≪クリニックの開業準備で陥りやすい失敗の例≫
クリニックの開業準備で陥りやすい失敗として、以下のような例が挙げられます。
- ●開業までのスケジュールが管理できておらず、開業予定日までに準備が間に合わなかった
- ●医療機器や什器・備品の購入費用がかかりすぎ、開業後の運転資金に余裕がなくなった
- ●看護師や受付の事務員などのスタッフ採用がうまくいかず、人手不足の状態で開業することになった
- ●集患・増患のための施策が不足しており、開業後に患者がほとんど来なかった
クリニックの開業を成功させるには、開業までのスケジュールを立て、計画的に準備を進めることが大切です。不安な方は、医院づくりの専門家に相談し、資金計画やスタッフの採用・研修、広告宣伝などについてアドバイスを受けるとよいでしょう。
≪まとめ:成功するクリニック開業の手順やポイントを知ろう≫
クリニックの開業には、診療圏調査や事業計画書の作成、開業する物件選び、内装工事の発注や医療機器の購入など、さまざまな準備が必要です。あらかじめ開業スケジュールを立て、計画的に準備を進めましょう。
クリニックの開業資金の目安は、5,000万~8,000万円程度と言われています。開業後に運転資金が枯渇することがないように、余裕を持って資金調達をすることが大切です。

























_s.jpg)


